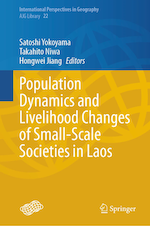
Yokoyama, S., Niwa, T. and Jiang, H. eds. "Population Dynamics and Livelihood Changes of Small-Scale Societies in Laos" Springer.
2025年5月8日発売、251ページ.
本書では、人口変動と生業変化を関連付けて、ラオスの3つの小規模社会におけるさまざまな動向を考察しています。本書では主に、(1)小規模社会における人口動態と生業変化の関係、(2)ラオスの農村部における現在の人口動態の傾向、(3)小規模社会の生業の維持、(4)開発途上国に共通する急速な人口増加の管理に着目しています。統計データが十分に整備されていない発展途上国におけるこれらの課題を研究するため、地理学、文化人類学、人類生態学、人口学を専門とするメンバーから構成される研究チームで実施した現地調査による情報をベースに民族誌としてまとめました。本書には、現代ラオス農村部における人口増加率の鈍化に関する貴重な情報を提供すると共に、生業、家族計画、人口移動の動向、さらに農村部における現代的な避妊方法の普及過程、高地から低地への移住を促す政府の再定住政策の影響を受けた、農村部間および農村部と都市部間の人口移動についても論じています。


